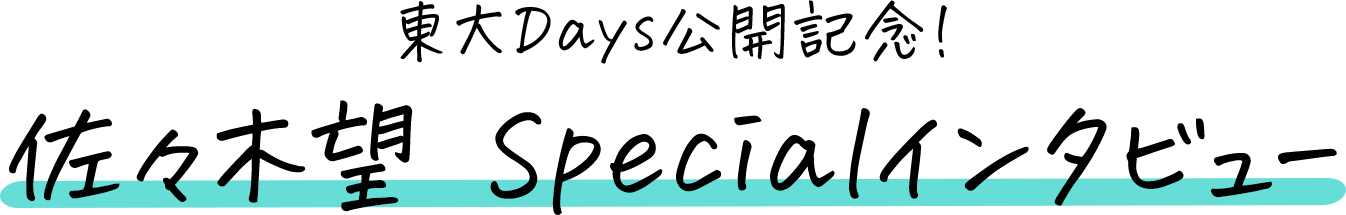2013年に東京大学を受験し合格、この春(2020年)法学部を卒業した声優・佐々木望。
魅惑的なボイスで数々のキャラクターを演じ、人気と実力をあわせ持つ声優としてそのキャリアを重ねてきた彼が、仕事をしながら東大に入学し卒業したという発表は、私たちを心底驚かせた。しかも文系トップとされる東大法学部である。
いったいなぜ? どうやって? 何のために? 聞きたいことは山ほど浮かんでくる。
「東大Days ―声優・佐々木望が東京大学で学んだ日々―」公開記念のこの独占インタビューでは、受験から入学、キャンパスライフ、勉強のことなど、東大生としての日々を佐々木さんに伺ってみる。
インタビュアー:漫画編集者 永田裕紀子
-
雨の早朝、ロンドン北西部に出かけます。
セント・ポールズ駅から歩いてすぐのところにある、クライストチャーチ・グレイフライアーズ・チャーチ・ガーデンに行ってみます。
もともとこの場所に建っていたグレイフライアーズ教会は第二次世界大戦で破壊され、現在は庭園になっていますが、教会の塔や壁は今も残っています。そこから数分歩くと、ロンドン中央刑事裁判所(通称「オールド・ベイリー」)です。
ここにはもともと、凶悪犯罪者を収容し、処刑していたニューゲート監獄がありました。
18世紀から19世紀に書かれた多くの小説や実話記にもたびたび登場しています。
ディケンズはここを見学して「ニューゲート監獄訪問記」を書きました。
※チャールズ・ディケンズ著、藤岡啓介訳『ボズのスケッチ』未知谷、2013年
グレイフライアーズ教会の跡
ロンドン中央刑事裁判所さらに歩いて、聖バーソロミュー・ザ・グレート教会に着きました。
ロンドンに現存する教会のうち、最古のものです。
「フォー・ウェディング」、「恋に落ちたシェークスピア」など、数々の映画に登場しています。隣接する王立聖バーソロミュー病院(通称「バーツ」)は、12世紀に設立された、現存するヨーロッパ最古の病院です。
シャーロック・ホームズがバーツの卒業生ジョン・ワトソンと初めて出会った場所です(フィクションですけどね)。
イギリスのドラマ「シャーロック」のロケ地にもなっています。
映像のホームズは、個人的には「シャーロック・ホームズの冒険」でジェレミー・ブレットが演じたホームズで固定されているのですけど、ベネディクト・カンバーバッチのホームズもかっこいいですね。病院の敷地内に聖バーソロミュー・ザ・レス教会があります。
その並びにある聖バーソロミュー病院博物館では、病院の歴史をたどる文書資料、歴代使用されてきた外科器具、病院の運営にも関わった画家ウィリアム・ホガースの壁画などを見ることができます。
小さい博物館ですが、とても魅力的なところです。展示室の入り口に、ホームズとワトソンがここ(病院の病理学研究室)で出会ったと記されている銘板が飾られていました。
初対面のワトソンに対して、あなたはアフガニスタンに行っていたのでしょうとホームズが言い当てた、『緋色の研究』の有名なシーンです。
銘板の存在は聞き知っていましたが、てっきり病院の中にあるものだと思っていたので、思いがけず博物館の中で見つけてシャーロッキアンの血が一瞬で沸き立ち瞳孔が拡大しました。
※コナン・ドイル著、阿部知二訳『緋色の研究』東京創元社、1960年通りに出て、聖バーソロミュー病院を回り込むように歩くと、スミスフィールド・マーケットがあります。
古くからある、ロンドン最大の食肉市場です。
ここは、かつては家畜の売買場、祭典の会場、そして公開処刑場でもあったようです。
当時は家畜売買も処刑もフェスティバルのようなものだったということなのでしょうかね。
映画「ブレーブハート」で描かれたスコットランド独立戦争の英雄ウィリアム・ウォレスもここで処刑されました。
先ほど行った聖バーソロミュー・ザ・レス教会のすぐそばに、ウォレスの慰霊碑があります。
聖バーソロミュー病院
スミスフィールド・マーケットあの、どうも道を間違えたようです。
次の目的地まで歩いて10分程度のはずが、スミスフィールド・マーケットの周りをてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくくるてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてく30分近くさまよいました。着きましたロンドン博物館。巨大な市立博物館です。
有史以前から現代まで、時代ごとにロンドンの歴史をたどることができます。ヴィクトリア朝時代のロンドンの街並みを再現した展示が圧巻です。
ガス燈、二輪馬車、仕立屋、煙草屋など、ディケンズやホームズの世界がそのまま目の前に広がります。
※アレックス・ワーナー著、日暮雅通訳『写真で見るヴィクトリア朝ロンドンとシャーロック・ホームズ』原書房、2016年ガス燈といえば、映画の「ガス燈」にはソロルド・ディキンソン監督のイギリス版(1940年)とジョージ・キューカー監督のアメリカ版(1944年)がありますが、まだイギリス版を観られていないままだったので、帰国したら早速手配しなければ、とヴィクトリア朝の街並みの中で思っていました。
展示では、労働者階級の貧困を写した19世紀後半の写真群も印象的でした。
ヴィクトリア朝時代に開校された貧困層の子どものための学校が、現在は博物館になっていると知りました(ロンドン北東部にある貧民学校博物館)。
大変興味があります。
今回はそこまで足を伸ばせませんでしたが、次回のロンドン再々訪では必ず行こうと決意しました。
※サラ・ワイズ著、栗原泉訳『塗りつぶされた町 ─ヴィクトリア期英国のスラムに生きる』紀伊國屋書店、2018年ところで、時代はヴィクトリア朝から現代へきゅるきゅる戻ってまたブリティッシュ・シネマの話になりますが、ケン・ローチ監督の労働者階級の人々を描いた作品が好きです。
1966年の「キャシー・カム・ホーム」(これは映画ではなくてBBCのテレビドラマですが)や、1981年の「まなざしと微笑み」が特に気に入っています。
60年代では他に、カレル・ライス監督「土曜の夜と日曜の朝」、トニー・リチャードソン監督「蜜の味」がいいですね。何度でも観てしまいます。イギリスのドキュメンタリーに「UPシリーズ」という番組があります。
1964年の「7 Up」が始まりで、異なる生育環境にいる7歳の子どもたち何人かにインタビューをしたものなのですが、それ以後も7年おきに、その同じ子どもたち(後に大人になられますが)それぞれに、人生についてインタビューをしていくんです。
14歳の時に「14 Up」、21歳のときに「21 Up」、みたいに、同じ人たちをずっと追ってきて、最新のは63歳の「63 Up」になっています。
7歳のときに話していた将来の夢そのままの人生を送っている方も、それとはまったく違う人生になっている方も、大人になってからいろいろな変遷をたどられた方もいらっしゃいます。イギリスのように、階級や階層があるとされる社会で、実在する複数の人たちの生を半世紀以上にわたって観て(「観る」というのは失礼かも。「見守って」、ですかね)いけるのはとても興味深いです。
現実に生きる人間の現実の人生に興味があるのは、自分が演技者だからというのが大きいのかもしれません。
これ、いきなり「42 Up」とか途中から観てもあまり意味ないと思うので(いやわかりませんけど)、ふつうは観るなら「7 Up」から順々にでしょうけど、全部観るのは何日もかかりますし、かなりお腹いっぱいになります。……そうでした、まだロンドン博物館にいたんでした。
展示物をひととおり見たらショップものぞいてみます。ショップには、当時サフラジェットがキャンペーンのために販売していたグッズのレプリカがありました。
サフラジェットとは、女性参政権を求めて19世紀末から20世紀初頭に活動した「女性社会政治連合」(WSPU)のメンバーたちを指す名称です。
団体の本拠地がロンドンにあったのですね。
ポスター、マグカップ、バッチ、ブローチなどの女性参政権運動グッズを興味深く鑑賞しました(そしてバッジを買いました)。ロンドン博物館の外にシティ・ウォール(市壁)という遺跡があります。
ローマ軍がイギリスを支配していた2世紀後半から3世紀に、大昔ですね、造られた城壁の跡地です。
ロンドン博物館
ロンドン博物館裏のシティ・ウォールまた歩き出します。
今度は迷わずにまっすぐ10分ほど、ロンドンの金融街であるシティ・オブ・ロンドンにセント・ポール大聖堂がそびえています。
巨大です。文字通りの大聖堂で威風堂々です。
時間の都合があって今回はドームの上までは登れませんでしたが(528段あるんですと)、健脚のうちにきっとまた来ます。セント・ポールズ駅に戻り、ダブルデッカー(ロンドン名物の赤い二階建てのバスです)に乗ってホルボーンまで行きます。
大英博物館の近くにちんまりひっそりと存在するカートゥーン博物館を見学します。
カートゥーンだから漫画なのですが、日本の漫画はでなくて、18世紀半ば頃からのイギリスの漫画や風刺画が紹介されています。
こちらは旅先では「なんでも見てやろう」の精神でいるので構わないのですが、正直に言うと、想像していた「カートゥーン」とも「博物館」とも相当に異なっていました。
いえ、面白かったんですけどね。
※カートゥーン博物館はその後、近隣に移転したようです。展示スペースはおそらく前よりも広くなっていると思われます。イギリスの漫画というと、子どもの頃大好きだった「アンディ・キャップ」を思い出します。
イギリスの日刊紙「デイリー・ミラー」に1957年から連載されていた新聞漫画です。
のんべえで賭事好きでダメ亭主のアンディは、私が今回のイギリス旅行で最初に訪れたダラム州にある港町ハートルプールに住んでいます(という設定です)。
※レジナルド・スマイズ著、大橋巨泉/奥山侊伸訳『ずっこけ亭主 アンディキャップ』ツル・コミック社、1970年
※Reg Smyth, Andy Capp at 50: Celebrating Half a Century of Laughs. David & Charles, 2006.当時は大橋巨泉さんらが翻訳をした日英対訳版が発売されていました。
アメリカのコミック「ピーナッツ」シリーズや「ビートル・ベイリー」シリーズとともに、買い揃えて熟読していました。
英語の勉強にもずいぶんとなりました。
それ以上に、これらコミック3作品の主人公たち(ビートル・ベイリー、アンディ・キャップ、「ピーナッツ」からは特にライナスとシュレーダー)は私の人格形成にも大きく影響を与えたように思います。
※チャールズ・M・シュルツ著、谷川俊太郎訳『完全版 ピーナッツ全集』河出書房新社、2020年
※モート・ウォーカー著、根本畏三訳『陽気なビートル二等兵』ツル・コミック社、1971年
※Mort Walker, Beetle Bailey: The Daily & Sunday Strips 1965. Titan Books, 2010.
カートゥーン博物館
歴史ある建物の一階はロンドン大学の大型書店ブルームズベリ・セントラル・ バプテスト教会を見学してから、大英博物館の横を通ってラッセル・スクエアまで歩きます。
ロンドン各地が舞台になったミステリは数多くありますが、ここブルームズベリ辺りを歩いていると、アントニー・バークリーの短編「ブルームズベリで会った女」(原題:Mr. Bearstowe says)が想起されます。
※アントニー・バークリー著、島田三蔵訳「ブルームズベリで会った女」(「ミステリマガジンNo.311」収録、早川書房、1982年)
※Anthony Berkeley, The Avenging Chance and Other Mysteries from Roger Sheringham's Casebook. Crippen & Landru Publishers, 2004.バークリー作品の中では、別名フランシス・アイルズ名義で書かれた『殺意』と『レディに捧げる殺人物語』が特に好きで何度も読んでいました。
『殺意』は、クロフツの『クロイドン発12時30分』、リチャード・ハルの『伯母殺人事件』とともに倒叙ミステリの3大傑作と言われていますが、倒叙ミステリというよりは犯罪心理小説という方が近いように思います。
※フランシス・アイルズ著、大久保康雄訳『殺意』東京創元社、1971年
※フランシス・アイルズ著、鮎川信夫訳『レディに捧げる殺人物語』東京創元社、1972年
※F・W・クロフツ著、大久保康雄訳『クロイドン発12時30分』東京創元社、1959年
※リチャード・ハル著、大久保康雄訳『伯母殺人事件』東京創元社、1960年ラッセル・スクエアに着きました。
この辺りは、ロンドン大学のカレッジと関連機関が集中している、いわゆる文教地区です。
ロンドン大学本部(Senate House)、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)、ブルネイ・ギャラリー、王立演劇アカデミー(RADA)、ピートリー・エジプト考古学博物館、グラント動物学博物館などを見学します。
王立演劇アカデミー(RADA)
グラント動物学博物館その後、会いたい人に会うべく、ロンドン大学のカレッジで最も歴史の長いユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の建物に向かいます。
建物1階のホールの隅に木製のキャビネットが設置されています。
私が会いたい人というのは、このキャビネットの中に座って(保管されて)おられるベンサム先生です。ジェレミー・ベンサム(1748-1832)はイギリスの哲学者、法学者です。
「最大多数の最大幸福」で知られる功利主義の提唱者でもあります。
本人の遺言により、ご遺体は加工されて(一部はミイラ、一部は蝋人形のような感じです)、UCLに展示されているのです。
ステッキを持ち帽子をかぶった生前のお姿でです。
※土屋恵一郎著『怪物ベンサム 快楽主義者の予言した社会』講談社、2012年法学を学ぶ者としては、ロンドンに来てベンサム先生のお姿を拝まずに帰るわけにはいきません。
いえまあ、いきませんということはないですけど、ロンドン大学といえばベンサム先生です。
拝見したいではないですか。ところが、私が行ったとき、いつもは開いているはずのキャビネットの扉は閉まっていました。
今も大学の評議会が開催されるときはベンサム先生も「出席」されるそうですので、この日も会議のためキャビネットを留守にされていたのかもしれません。
※会議の議事録には、「ベンサム先生は出席、しかし投票には加わらなかった」と記載されるそうです。扉の閉まったキャビネットを見て落胆していると、大学のスタッフさんが話しかけてくださいました。
同情して、なのか、単に怪しい奴に見えたからなのかは不明です。
隣の建物で法学部の公開討論会があるので参加してみれば、と案内してくださったのですが、あいにくそこまでの時間がなかったので、討論会の会場を見るだけにして大学を出ました。大英博物館まで歩いて戻ります。
すでに夕方になっていましたが、金曜の夜は遅くまで開館していてくれているので、まだあと数時間あります。
とはいえ世界最大級の博物館なのですべてをしっかり見るのは無理ですが、まず最上階に上がって、そこから超速足で時間いっぱいまで見ていきました。連日歩きまくっているので、脚が大変に鍛えられています。

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)
ベンサム先生は本日ご不在です
夜の大英博物館
ロンドン滞在記 〜 4日目 〜
-
今日は滞在最終日です。
ホテルからホルボーン駅方面に歩き、セント・アンセルム&セント・セシリア教会を訪れます。
さらに歩き、コヴェント・ガーデン駅、レスター・スクエア駅を超えて、ロンドンのチャイナタウンに入ります。
ロンドンの劇場や映画館が立ち並んでいる角を曲がると、すぐに中華街の大きな門が立ち現れるので、一瞬、自分が世界のどこにいるのかわからなくなります。中華街の門の手前に、歴史あるミニシアターのプリンス・チャールズ・シネマがあります。いわゆる名画座です。
時間があれば映画も観たいところでした。その並びにあるノートルダム・ド・フランス教会に入ります。
小さく美しい教会です。
今日は特にここに来てみたかったのです。ここは、「コクトー・チャペル」とも言われています。
フランスの芸術家ジャン・コクトーが描いた壁画があるのです。
壁画は持ち込まれたものではなく、1959年にコクトーがロンドンに来て描いたそうです。
小説『ダ・ヴィンチ・コード』には、コクトーとこのノートルダム・ド・フランス教会が登場しています。
※ダン・ブラウン著、越前敏弥訳『ダ・ヴィンチ・コード(上・中・下)』角川書店、2006年コクトーの小説では、『恐るべき子供たち』、『大胯びらき』などを読んできました。
近年、戯曲の『声』が発売されたのも嬉しいです。
映画では、ジャン=ピエール・メルヴィルが監督した『恐るべき子供たち』がやはり恐ろしい。
コクトー自身が監督した「恐るべき親達」という映画にも興味がありますが、これはまだ観る機会がありません。
※ジャン・コクトー著、鈴木力衛訳『恐るべき子供たち』岩波書店、1957年 ※ジャン・コクトー著、澁澤龍彦訳『大胯びらき』河出書房新社、2003年 ※マルグリット・デュラス/ジャン・コクトー著、渡辺守章訳『アガタ/声』光文社、2010年話は飛びますが、メルヴィル監督の映画には他にいくつも好きな作品があります。
「モラン神父」と「リスボン特急」は自分の好みのツボに入ります。
「海の沈黙」は、ただただすばらしい。澁澤龍彦の著書の挿絵を手がけられたりした金子國義画伯の絵が好きです。
澁澤さんと金子さんは私的にも交流があって、当時は金子さんたち芸術家が鎌倉の澁澤邸に集っていたという話を、川村万梨阿さんからつい先日伺いました。
このエピソード自体も興味深いですが、友人(川村さんは声優の先輩ですが、同時に長年の大切な友人でもあります)とこのような話ができることも嬉しいです。教会の中でコクトーの壁画を観て回ります。
ひんやりとした静かな空間です。
自分の足音しか聞こえません。
礼拝用のベンチに横たわって眠っている(おそらくホームレスの)人が何人もいらっしゃったことに気がついたのは、入ってずいぶん経ってからでした。教会を出てレスター・スクエア駅まで歩きます。
ここからコヴェント・ガーデンにかけてのウエスト・エンド地区は、劇場街になっています。
ロンドン初日に行ったセブン・ダイアルズの近くに戻ってきたことになります。
アガサ・クリスティ原作の舞台「ねずみとり」を1952年から上演しているセント・マーティンズ劇場もこの辺りにあります。レスター・スクエア駅の東側にある六差路に、アガサ・クリスティの記念碑があります。
クリスティは、モーリス・ルブラン(アルセーヌ・ルパンの作者)、コナン・ドイル(シャーロック・ホームズの作者)に続いて出会った(=知った/読んだ)推理作家で、私にとっては数十年来の思い入れがあります。
ノートルダム・ド・フランス教会
アガサ・クリスティ記念碑小学生のときに、クリスティの文庫本に誤植が1箇所(といっても組版上のエラーで、文自体に支障があったわけではありません)あると指摘するハガキを東京創元社さんにお送りしたことがあるのですが、子どもの手紙に対しても丁寧なお礼状をいただいて、とても嬉しかった記憶があります。
というか、子どもの頃から細かい奴だったのですね私は。以前、『銀河英雄伝説』の田中芳樹先生とイベントでご一緒させていただいたときに、楽屋でお話をさせていただく機会があったのですが、クリスティの小説を話題に二人でプチ盛り上がったことがあります。
そもそもどういう経緯でそんな話になったのか、クリスティの短編の中で「うぐいす荘」を読んだときの鮮烈な衝撃を超えるものはないと申し上げたところ、田中先生も「『うぐいす荘』、ええ、ええ、あれはいいですね」とおっしゃってくださったのでとても嬉しかったのです、ユリアンとしては(いやユリアン関係なく)。
※アガサ・クリスティ著、中村能三訳「夜鶯荘」(江戸川乱歩編『世界推理短編傑作集3』収録、東京創元社、2018年)
※アガサ・クリスティー著、田村隆一訳「ナイチンゲール荘」(『リスタデール卿の謎』収録、早川書房、2003年)クリスティの短編に「検察側の証人」という作品があります。
この映画版である「情婦」が最高に面白いのです。
個人的に、「私の選ぶ映画100選」というリストを作ったことがありますが(そのリストはまだどこにも出していないのですけど)、「情婦」は私の100選どころかトップ10選に入る映画です。
しかし、なんとなくですが、「情婦」というタイトルは観てくれる人を一定数逃しているような(あるいは、別ジャンルの映画だと一定数の人に期待させてしまうような)。
法廷ミステリなので、タイトルは「検察側の証人」のままでよかったのにと思います。
※アガサ・クリスティ著、厚木淳訳『検察側の証人』東京創元社、2004年
※アガサ・クリスティー著、加藤恭平訳『検察側の証人』早川書房、2004年そうそう、イギリスの推理作家といえばもうひとり、ルース・レンデルも好きです。
“last but not least" という英語のフレーズがありますけど、まさにこういうときに使うのでしょう。last but not least
used when mentioning the last person or thing of a group, in order to say that they are not less important than the others(from the Oxford Advanced Learner's Dictionary)人や物を挙げていくときに、最後になってしまった人/物について、最後(last)になったとしても(but)重要度が超低い(least)わけではまったくない(not)んですよ、同じように重要ですよ、という意味の言い回しです。
レンデル作品の多くも、推理小説というよりは犯罪心理小説、あるいはサイコ・スリラーという方が近いです。
レンデルの翻訳本が刊行され始めた1980年代に読みまくっていました。
ほんっとに面白いです。
面白いミステリ系の本を何か教えてと言われると、とりあえず『わが目の悪魔』や『ロウフィールド館の惨劇』をお薦めしたりしています。
※ルース・レンデル著、深町眞理子訳『わが目の悪魔』角川書店、1982年
※ルース・レンデル著、小尾芙佐訳『ロウフィールド館の惨劇』角川書店、1984年レンデルさんがスウェーデン生まれだというところから話を展開(≒脱線)させますと、スウェーデンの警察小説「マルティン・ベック」シリーズ(全10作)には独特な魅力を感じます。
自分がかつて読んでいたのは英訳版を日本語に翻訳した重訳版でしたけど、原著からの翻訳が近年刊行されたと知りました。
こちらもあらためて読んでみたいです。
※マイ・シューヴァル/ペール・ヴァールー著、柳沢由実子訳『刑事マルティン・ベック 笑う警官』角川書店、2013年北欧ミステリといえば、「スハウエンダム~12の疑惑~」というオランダのミステリドラマに吹替で出演しています。
ご覧いただけると嬉しいです。
https://nozomusasaki.com/contents/329268で私いまどこにいるんでしたっけ?
そうでした、レスター・スクエア駅近くのアガサ・クリスティ記念碑の前に立っていたのでした。
昨日、ホームズの舞台となった聖バーソロミュー病院に行ったときもそうでしたけど、ここクリスティの記念碑も、感慨深くてちょっと立ち去りがたいです。朝来たホルボーン方面に戻ります。
コヴェント・ガーデン駅を越えててくてくてくてくてくてくてくてくてく15分くらいてくてくてくてくてくてくてくてくてく歩くと、リンカンズ・イン・フィールズという公園があります。
映画で見たことのある(気がする)ようなところです。
しばらくベンチに座って、人々が犬を散歩させたりキャッチボールをしたりしているのを眺めていました。リンカンズ・イン・フィールズに面して、ジョン・ソーン博物館があります。
ジョン・ソーン卿は、18世紀の終わり頃から19世紀にかけて活躍した建築家で、ここは彼の自邸でした。
立ち並ぶ住宅の中で、この博物館も一見したところ普通の住宅に見えるのですが、中に入ると別世界が広がっています。
ソーン卿が世界中から収集したおびただしい数の美術品や骨董が、1837年の開館当時からそのまま保管してあるのです。
決して大きくはない邸宅の、壁も通路も天井も、どこを向いてもコレクションで覆い尽くされています。
リンカンズ・イン・フィールズ
ジョン・ソーン博物館ホルボーン駅からピカデリー線に乗り、キングス・クロス・セント・パンクラス駅で降ります。
そこから2、3分歩くと大英図書館に着きます。
夕方には空港に行っていないといけないのでほとんど時間が残っていませんが、世界最大級の国立図書館にどうしても寄っておきたかったのです。大英図書館には、マグナ・カルタの原本、シェイクスピアやシャーロット・ブロンテの原稿、モーツァルトの楽譜、レオナルド・ダ・ヴィンチのノートなど数々のコレクションが展示されています。
展示エリアを急いで観て、外に出てダブルデッカーのバスに乗ります。
ホテル近くまで一番早く行けるはず。
キングス・クロス・セント・パンクラス駅
大英図書館ダブルデッカーのバスは赤くてかわいいけど、自分がダブルデッカーに乗っている間は赤くてかわいいダブルデッカーを見ることはできないのだな、などとぼんやり考えたりしていましたが、ふと気がつくと、バスがあまり進んでいません。
道が混んでいるようです。思ったよりもホテルまでずっと時間がかかりそうです。
地図を見ながら現在どこを走っているのかを把握しようとしていたのですが、途中から、そのバスの通常のルートとは違う道を走行していることに気がつきました。
いつもの道が工事か何かで通行規制中なのかもしれません。
これは遠回りになっているな、時間は大丈夫だろうかと心配になってきました。バスのアナウンスが流れました。
聴き取りがなかなか難しいです。
どうも、何かの特殊な事情により終点までは行けないと言っているように聞こえます。
まじですかそれ。聞き違いでしょうか。
でも、もし聞き違いでなければ、このバスの変更後の終点からさらにバスかタクシーを乗り継いでホテルに戻らなければならなくなります。
そうなると予定の時間に絶対に間に合いません。信号と渋滞とでまたバスが止まりました。
何分も動きません。
外を見ると、地下鉄の駅のマークが目に入りました。
バスを飛び降りて(これは比喩表現です)、地下鉄でホテルのある駅に帰ります。
普段のもっさりした自分からすれば、めずらしく機敏な行動です。ホテルに預けてあったスーツケースを受け取ると、大急ぎでヒースロー空港に向かいます。
なんとか帰国便に間に合いました。これでイギリスの旅は終わりです。
いろいろとお世話になりました。
アイラブロンドン。ダラムも。ニューカッスルも。
ロンドン滞在記 〜 5日目 〜
- 良いご旅行だったんですね! では休学中のお話をもう少しお伺いできますか?
- 佐々木 はい。
noteでもお読みいただけます!
バックナンバー
- 東大法学部を卒業した声優に、スタッフがまだもうちょっと聞いてみたいこと ②
- 東大法学部を卒業した声優に、スタッフがまだもうちょっと聞いてみたいこと ①
- Vol.20 法学徒の本気 〜2019年秋、本郷〜
- Vol.19 法学徒の進撃 〜2019年春、本郷〜
- Vol.18 法学徒の苦心 〜2018年秋、本郷〜
- Vol.17 法学徒の足どり 〜2018年春、本郷〜
- Vol.16 法学徒の休学② 〜2017年春、ロンドン〜
- Vol.15 法学徒の休学① 〜2017年春、ロンドン〜
- Vol.14 法学徒の判断 〜2016年秋冬、本郷〜
- Vol.13 法学徒の発見 〜2016年夏、本郷〜
- Vol.12 法学徒の基底 〜2016年夏、本郷〜
- Vol.11 法学徒の自覚 〜2016年春、本郷〜
- Vol.10 法学徒の手探り 〜2016年初頭、本郷〜
- Vol.9 法学徒の脇道② 〜2014年冬、駒場〜
- Vol.8 法学徒の脇道① 〜2014年冬、駒場〜
- Vol.7 法学徒の選択 〜2015年冬、本郷〜
- Vol.6 法学徒の模索 〜2015年秋、本郷〜
- Vol.5 法学徒幼年期 〜2015年夏、本郷〜
- Vol.4 或る法学徒の誕生 〜2015年春、本郷〜
- Vol.3 駒場を満喫し尽くそう! 〜スペ語と友と進振りと〜
- Vol.2 駒場のキャンパスライフ 〜東大1年生スタート!〜
- Vol.1 東大入学への軌跡 〜なぜ? どうやって東大に?!〜